矯正治療で歯を狙いどおりに動かすには、ワイヤーを曲げて力を調整する「ワイヤーベンディング(屈曲)」が欠かせません。
なかでも、ワイヤーにループを組み込んで抜歯スペースを閉じる「ループメカニクス」は、臨床で最も頻繁に用いられる基本テクニックの一つです。
この記事では、代表的なループの種類とそれぞれの役割を整理し、操作のポイントをわかりやすく解説します。
ループメカニクスとは?
ループメカニクスとは、ワイヤーにループを加えてスペースを閉じる手法のことです。
ループメカニクスの概要については、下記の記事が参考になります。

抜歯スペースの閉鎖に用いるループは総称して“クロージングループ”と呼ばれますが、実際には目的別に複数のタイプがあります。
クロージングループの代表例:「Vループ」を解説

クロージングループとは、抜歯スペースを効率よく閉じるために設けるループです。
クロージングループで最も代表的なのが「Vループ」です。
Vループは、その名の通りV字型のベンドがワイヤー上に作られています。
「Vループの概要」
・使用位置:抜歯スペース(例:2番と3番の間など)
・特徴:比較的作りやすく、力の方向性がコントロールしやすい
・目的:ループの開閉を利用し、前歯を後方に引き込みながらスペースを閉じていく
Vループは抜歯スペースを閉鎖するだけでなく、症例によっては臼歯を前方へ移動させる目的でも活用されます。
ループを開閉して力を加える操作は「アクチベート」と呼ばれ、この戻る力を段階的に利用してスペースを計画的に閉じることが可能です。
クロージングループだけじゃない:ストップループの役割
ループメカニクスでは、大切なループの一つに「ストップループ」があります。
「ストップループの概要」
・設置場所:基本的には6番と7番の間に設置
・役割:
・クロージングループを開いた状態でキープする
・固定源の強化(臼歯が前方に移動(ロス)してしまわないようにするストッパー機能)
ストップループの代替としては、ロウ着によって固定を行う方法もあります。
その他のループ:Lループ(マルチループ)
複雑な動きや大きな可動域が必要な症例では、「Lループ(またはマルチループ)」が選択されることがあります。
「Lループの概要」
特徴:
・剛性の高いワイヤー(SSなど)に対し、三次元的な可動域を持たせる構造
・ループ形状によって上下左右方向への調整が可能
用途:
・咬合平面の調整
・移動量の多い部位の力のコントロール
・歯軸の細かいコントロール
Lループは、治療の自由度が高まる反面、設計や調整には高い技術力と経験が求められます。
それぞれの歯に対して全てマルチループを設定したワイヤーテクニックを、MEAWテクニックと呼びます。
ループ操作で重要なこと:設計と反復練習

ループを使った治療は、力の方向と大きさをコントロールできる反面、その効果を最大化するには、ループの形状・サイズ・位置・角度を症例に応じて調整する必要があります。
ループ操作が上手くいかないと、次のようなトラブルが生じる可能性があります。
・ループの大きさや角度によっては、清掃性や違和感が問題になる
・小さすぎると、十分な力が得られない
・角度の微調整で、歯の移動方向が大きく変わる
ループ操作では、設計と反復練習が重要です。
チェアタイムはやや長くなりますが、毎回のベンド操作が“治療精度そのもの”に直結するので、技術を磨いていきましょう。
まとめ:ループの種類を理解して治療の幅を広げよう
今回紹介した3つのループについて、用途と特徴をまとめました。
| ループ名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| Vループ | 抜歯スペースの閉鎖(クロージング) | 作製しやすく、前歯の牽引に適する |
| ストップループ | アクチベートで利用、固定源補強 | 6・7番間に設置。ロウ着の代替にも◎ |
| Lループ(マルチ) | 三次元的コントロールが必要な症例 | 可動域が広く、高い操作性。経験値が必要 |
症例に適したループを選んで、矯正治療を成功させましょう。
矯正を学ぶドクター・衛生士の皆さんへ
ループの活用は、矯正力の方向性を“自在に設計する”ための武器です。
慣れるまでは少し時間がかかりますが、設計の意図を理解しながら反復練習すると、チェアサイドの精度とスピードが格段にアップします。
ループメカニクスは「難しいからやらない」ではなく、「知っていれば戦略が増える」領域です。
ぜひ日々の臨床に活かしてください!
ミノアカライブラリーを運営するMino’akaでは、矯正スタディグループMino’aka Ortho Academiaとして年4回の矯正勉強会を開催しています。
現役の矯正医や一般医が参加し、積極的に交流しながら実践的なレクチャーを行っています。
Instagramでも日々歯科矯正に関する情報を発信していますので、参考にしてください。
今後も技術を磨きながら、より良い矯正治療を実践していきましょう!

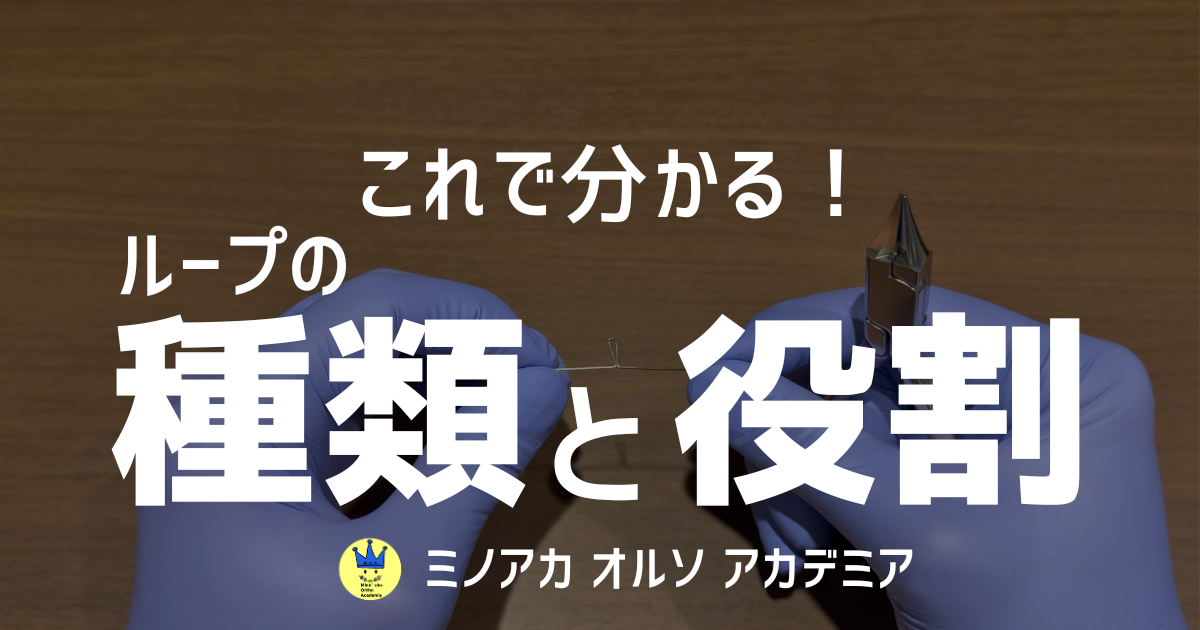
コメント